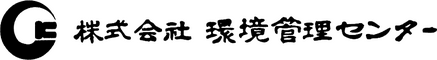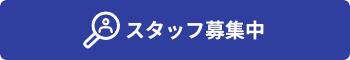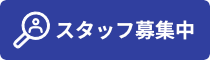| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
769/1000 今年最後の儀式
2025/12/26
私は父の会社を継いだから、
仕事というのは、これしかないと思ってきた。
それでも、ときどき思う。
本当は、自分は何をしたいのだろう、と。
腕時計が好きだから、
「65歳になったら、時計屋さんにでもなろうかな」
と妻に言う。
「儲からなそう」
そう言って、妻は笑う。
でも私は知っている。
父から受け継いだのは、清掃という仕事だ。
そしてこの仕事をしているとき、
自分はいちばん幸せだということを。
楽な仕事ではない。
無理をすることもあるし、
しんどい現場もある。
それでも、現場に立っていると、
自分がちゃんと、ここにいる感覚がある。
私は、この仕事が好きだ。
そしてここが、
私がいちばん、活きる場所だ。
今年最後の空家整理の現場が終わった。
空き家から、どんどんモノが運び出されていく。
掃除機で、タンスの裏に溜まった
ヤニの混じった綿ぼこりを吸い、
ネズミのフンを箒で集めていく。
そうしているうちに、
家そのものが、深呼吸を始めるのが分かる。
この家は、解体されるという。
それでも、最後は掃き清める。
解体前の空家を、ここまで丁寧に清掃する業者は多くない。
ご依頼主から、特別な指示があるわけでもない。
けれど、これは私たちにとって大切な儀式だ。
ここにあった想い出を、
どこか天国みたいな場所へ送り出すための、儀式だ。
そんな、今年最後の儀式が終わった。
767/1000 7分間に詰め込まれた、5ヶ月分の本気
2025/12/24
今日は、
昨年はチャレンジャーとして参加していた
鶴岡イノベーションプログラム2025の事業構想発表会に参加してきた。
発表は6チーム。
どのチームも、本当に素晴らしかった。
大感動・大興奮。
その言葉以外、見当たらない。
ビジネス構想というのは不思議なもので、
プランの完成度以上に、
「どれだけ本気か」「どんな人なのか」が、どうしても表に出てしまう。
上手く話そうとしても、
格好よく見せようとしても、
覚悟の浅さも、迷いも、逆に強さも、全部滲み出る。
だからこそ、あの7分間は嘘がつけない。
7分間。
たった7分。
けれどその裏には、5ヶ月分の時間が詰まっている。
考えて、壊して、また考えて。
否定されて、揺れて、それでも前に進んできた濃密な時間。
その積み重ねが、会場の空気を一気に変えていく。
昨年、自分がその立場だったから分かる。
あの場所に立つまでが、どれほど濃厚かということを。
今日は聞く側だった。
けれど、心はずっと前のめりだった。
「いいな」
「この感じだ」
そんな気持ちが、何度も胸の奥で湧き上がった。
挑戦する人の姿を見ていると、
胸が熱くなって、
ズドーンと前向きな気持ちに導かれる。
最後に、このプログラムの発案者である
野村総研のチーフが語った話がある。
大きな岩は、一人では動かない。
仲間が必要で、時間も力もいる。
けれど、
たった一人でも「動かす」と決める人がいなければ、
その岩は、永遠にそこにあるだけだ。
そして、
今日ここはゴールではなく、スタート地点なのだということ。
この言葉は、
私も昔、師匠から教えられた言葉でもある。
当時は、正直よく分からなかった。
けれど、年を重ね、立場が変わり、
事業や人に向き合うようになって、
ようやく腹に落ちてきた。
私自身、
昨年このプログラムで描いたプランを、
いまも温め続けている。
形は変わり、スピードもゆっくりかもしれない。
それでも、
あの時見据えた岩を、今も動かし続けている。
ビジネスは、チームで動かすものだ。
けれど、始まりはいつだって一人の覚悟だ。
今日の6チームの7分間は、
その「始まり」を、はっきりと見せてくれた。765/1000 M-1ほど、ライブで見たくなるものはない
2025/12/22
昨日、漫才日本一を決める
M-1グランプリ が開催された。
そんな夜、親友からLINEが入った。
「M-1なんか、俺が緊張するわ〜」
思わず、少し笑った。
舞台に立つわけでもないのに緊張する。
けれど、その気持ちはよく分かる。
彼はエバース推しだった。
実は、私も息子も、やはりエバース推しだ。
決勝一回戦、エバースのネタは圧倒的だった。
空気を一気に持っていく力。
結果は一位通過。
「これはいったな」と、家の中の誰もが感じていた。
だが、M-1は最後まで分からない。
三組に絞られた最終決戦。
そこで一気に景色を変えたのが、たくろうだった。
たくろうのネタは、考えなくてもスッと入ってくる。
説明を待つ必要がない。
設定が提示された瞬間、もう頭の中に情景が浮かぶ。
気づけば笑っていて、
気づけば、その世界に入り込んでいる。
審査員の 塙宣之 さんが言っていた
「絵が見えるネタ」という言葉が、これほど腑に落ちたことはない。
その強度が、たくろうはずば抜けていた。
エバースの緊張感と構築力。
たくろうの没入感と自然さ。
どちらが上、という話ではない。
ただ、あの場面で、あの空気の中で、
一番深く刺さったのが、たくろうだった。
結果発表を見て、
息子は静かにうなずき、
私は少し悔しくて、それでも納得していた。
しばらくして、息子がぽつりと呟いた。
「M-1ほど、ライブで見たくなるものはないよね」
なるほど、と思った。
あの数分間は、編集もやり直しも効かない。
その場の空気、間、緊張、すべてが一度きりだ。
だからこそ、あれほど心を掴まれるのだろう。
この結果には、きっと誰もが納得だっただろう。
そして、わずか4分間のステージに、
どれだけの熱と時間を詰め込んできたのか。
そう想像した瞬間、胸の奥が、じんわりと熱くなった。
だから、他人事なのに緊張する。
だから、推しが負けても、拍手をしてしまう。
M-1は、笑いの大会でありながら、
本気で積み上げてきた時間を、
世代を越えて共有させてくれる夜なのだと思う。763/1000 クリスマスプレゼントのお話
2025/12/20
プレゼントを贈る日といえば、誕生日かクリスマス。
だいたいそんなものだろう。
大人になると、どちらも少しずつ形骸化していくが、
子どもにとっては世界の重心がそこにある。
今から10年ほど前。
保育園に通っていた息子が、サンタさんにお願いすると言い出したのが、
ペッパーだった。
あの白くて、しゃべって、感情表現をするコミュニケーションロボット。
屈託のない笑顔で、
「サンタさんなら持ってきてくれるよ」と言う。
当時の価格は20万円弱。
さすがにそれは…と、大人の側は顔を見合わせたが、
本人にはそんな事情は一切関係ない。
そして迎えたクリスマスの朝。
玄関先に置かれていたのは、ペッパーではなく、
スーパーファミコンミニだった。
「……ペッパーくんじゃない」
その一言と一緒に、息子の表情が少しだけ曇った。
申し訳なさと、これで良かったのだろうかという迷い。
そこで、
「どれどれ」と父である私がテレビに繋いだ。
マリオカート。
ストリートファイター。
コントローラーを握った瞬間、
指が勝手に動く。
昔とった杵柄とは、よく言ったものだ。
必殺技を出しまくり、少し得意げにやってみせた。
すると、息子の反応が変わった。
「え、なにそれ!」
「もう一回やって!」
さっきまでの落胆はどこへやら、
目がキラキラに変わっていく。
「どうだ、やってみるか?」
そう声をかけた瞬間、
サンタは確かに、そこにいたのだと思う。
そのゲーム機も、数年後、
妻がそれと分からず中古屋さんに売ってしまった。
よくある話だ。
けれど、小林家の食卓では、
「あのゲーム、またやりたいね」
そんな話題が、たまにのぼる。
サンタが来なくなって久しい小林家。
今年は、そのゲーム機をもう一度買おうと思っている。
驚かせたいのは、子どもたちなのか。
それとも、
あの頃の家族の時間なのか。
プレゼントとは、
モノを渡す行為ではなく、
同じ時間を思い出せる記憶を残すことなのかもしれない。
そんなことを考えながら、
今年のクリスマスを迎えようとしている。761/100 偉い、という二面性
2025/12/18
「偉い」という言葉には、
最初から二つの顔がある。
ひとつは、
行動に向けられる「偉い」。
続けている。
逃げずに向き合っている。
結果はともかく、ちゃんとやっている。
こういう場面で使われる「偉い」は、
人を前に進ませる言葉だ。
もうひとつは、
立場や自己評価に向けられる「偉い」。
もう分かっている。
ここまで来た。
教わる必要はない。
この「偉い」は、
少しずつ人を止めていく。
ややこしいのは、
同じ言葉なのに、
向きが変わるだけで意味が反転することだ。
人は誰でも、
自分を偉い場所に置きたくなる。
それ自体は自然なことだ。
ただ、その場所に居座り始めると、
空気が変わる。
質問が減る。
違和感が共有されなくなる。
そのうち誰も、
服の話をしなくなる。
裸の王様が生まれるときは、
たいてい静かだ。
偉さをまとおうとする行為は、
成熟ではなく、むしろ幼さに近い。
成熟している人ほど、
自分を「偉い側」には置かない。
分からない場所に立ち続ける。
「偉い」という言葉は、
使い方ひとつで、
背中も、足も止めてしまう。
だからこそ、
行動に向けて使うのがちょうどいい。
立場を守るための言葉になった瞬間、
その偉さは、
幼さに変わる。
-
 795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
-
 797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
-
 797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
-
 799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
明日から二泊三日の東京出張に備えて、段取り中。 大雪の庄内から晴天であろう東京へ行くので、まず靴から考える。
799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
明日から二泊三日の東京出張に備えて、段取り中。 大雪の庄内から晴天であろう東京へ行くので、まず靴から考える。
-
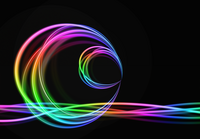 801/1000 経営というメンコ合戦
東京出張二日目。中期経営計画を立てる勉強会に参加している。利益、戦略、数字、未来。ノートを取りながら、改めて目
801/1000 経営というメンコ合戦
東京出張二日目。中期経営計画を立てる勉強会に参加している。利益、戦略、数字、未来。ノートを取りながら、改めて目