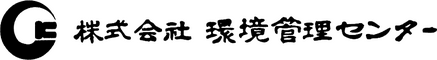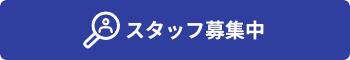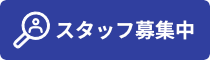| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
653/1000 無地のカーテンと、少し軽やかな人生
2025/08/31
築17年のわが家。ずっと使ってきたレースのカーテンが、この夏の光に少し黄ばんで見えた。朝日を受けるたびに、古びたレース越しの景色がどこか懐かしいセピア色をまとっている。
新築の頃は、カタログを隅から隅まで眺め、プロにも相談してやっと決めたカーテンだった。色や生地、光の透け方まで、こだわり抜いて選んだのを覚えている。それだけに、取り替えることには抵抗があった。
けれど今回は違った。ネットオーダーで「迷ったらこれ」にチェックが入っていた、ごく普通の無地のレース。届いた新品のオフホワイトをかけた瞬間、部屋の空気が一気に洗濯されたみたいに澄み、どこか品格まで上がった気がした。
家も人も、歳を重ねたからこその良さがある。壁の落書きや小さな傷だって、時間が刻んだ物語だ。そこに手を入れず残すものがある一方で、こうして入れ替えることで気づくこともある。
今では、こだわりに振り回されることもない。なんの変哲もないレースのカーテンが、いちばんしっくりくる。こだわりを手放したら、人生は少しだけ軽やかになった。無地のカーテンと一緒に。651/1000 肉の日に思う。食べ物だけが持つ魅力
2025/08/29
朝9時、街を走る車の窓から見えたのは、一軒の精肉店に続く長蛇の列。鶴岡ではなかなか見ない光景に、思わずハンドルを切りそうになった。そうか、今日は29日、肉の日か。
その瞬間、私の脳裏に浮かんだのはダチョウ倶楽部の寺門ジモンさんだった。芸能界一の肉通として知られる彼は、還暦を過ぎても焼肉で胃もたれしたことがないという。
ジモンさんは言う。脂はちゃんと焼けばパリッと仕上がり、むしろもたれないのだと。肉の質、包丁の入れ方、焼き方。どれもがそろって初めて、一枚の肉は芸術品になる。私のようにカルビを一気にかき込んで翌日後悔するのとは、まるで対極にある世界だ。
そんなジモンさんは、骨董品や時計などのコレクションでも知られている。だが彼はこう語る。
「いい物というのは、手に入れて倉庫に鍵をかけて終わり。結局、預かっているだけなんだよ」
確かに、コレクションは所有の喜びで完結する。いつかは誰かの手に渡る運命を持ち、持ち主は守り人でしかない。
ところが食べ物は違う。目で見て、香りを楽しみ、口に運び、身体に取り込み、自分の一部になる。所有ではなく、体験として完結する唯一の存在なのだ。
還暦を過ぎても肉を愛し、胃もたれ知らずでいられるのは、ジモンさんがこの“完結する体験”を人生の楽しみとして大切にしているからなのだろう。649/1000 花札から能の舞台まで──芒に月と食卓の会話
2025/08/27
昨夜の食卓で、末の娘が兄に尋ねた。
「ねえ、この曲のタイトル、なんて読むの?」
スマホから流れていたのは、椎名林檎さんの新曲『芒に月』。今年の6月に出たばかりの曲だが、“芒”の字は娘にはなじみがなかったらしい。
どこで知ったか知らないが、兄は少し得意げに答えた。
「“すすきにつき”って読むんだよ。花札の札がモチーフになってる。」
そこから食卓は、ちょっとした花札講座に。
「シカトって言葉も花札用語で、鹿の札を取られない=無視するって意味からきてるんだ。」
「へえ〜そうなんだ!」
家族みんなで感心しながら、私も横で初めて知ってうなずいた。さらに今日知ったトリビアとして、物事を終えるときに使う「仕舞う」も実は能の舞台から来ているという。舞の最後を納める所作を「仕舞い」と呼び、そこから物事を美しく終えることを「仕舞う」と言うようになったのだとか。
私たちお片付けの現場でも、この「仕舞う」をどうプロデュースするかがいつもカギになる。647/1000 ドームも神宮も横浜も、父まだ未経験
2025/08/25
お盆で帰省した娘が、最近ハマっているのは野球観戦だという。
巨人ファンで、なんと月に3回も東京ドームや神宮球場、横浜スタジアムに足を運んでいるらしい。
「イケメンが多いのはソフトバンクなんだよ。細マッチョが多くてさ」
スマホの画面を見せながら熱弁する娘。その写真の中に父親が入り込む余地は、もちろんない。
思い出すのは、彼女が高校1年の頃。母校が甲子園に出場した時、「せっかくだから応援に行ってこい」と言ったら、娘は一言、
「また行けばいいから」
あの時のあっけらかんとした返事が今も耳に残っている。
結局、あの夏は一度きりだったのに。
そんな娘が今や、プロ野球観戦に夢中だとは。
アラフィフの父はというと、ドームも神宮も横浜も、まだ一度も行ったことがない。
そのうち娘に連れて行ってもらおうか──そんなことをぼんやり考えている。
横で野球を全く知らない高校生の息子に、娘が熱弁をふるう。
「江夏豊っている?」と息子。
そんな会話を聴きながら、父はただビールを一口。
家族のこういう時間が、なんだかんだ一番面白い。645/1000 さあハロウィンがやってくる。 知らんけど
2025/08/23
三日前のこと。通勤の道すがら、ぽとりと栗が落ちていた。見上げると、葉の間にまだ丸々とした実がいくつもぶら下がっている。ああ、秋だなと思う。買い物に立ち寄った店では、ハロウィンの飾りがずらりと並び、かぼちゃのお化けが笑っている。子どもの頃にはなかった光景だ。
ハロウィンが日本にやって来たのは、私が二十代前半のころだっただろうか。だけど正直、いまだにその正体はよく分かっていない。
さて、もうひとつ、最近思い出したのが三遊亭円右師匠の「クリスマス」という落語である。戦後しばらくの日本人が、クリスマスという異国の行事を“よく分からないまま”受け入れていた頃の空気が漂っている。昔の落語家さんは、イブを大晦日、クリスマスを元旦のようなものだと説明していたそうだ。つまり年越しと同じように浮かれ、同じように迎えればいい。だけど庶民にとっては、やっぱり「なんのこっちゃ」である。
円右師匠の「クリスマス」は、ちょっと世知辛くて、でも人間くさい。聴いた人が「こんなクリスマスだけは嫌だ」と思ったというのも分かる気がする。そう考えると、ハロウィンやクリスマスは、分からないまま笑いながら受け入れてきた文化の象徴なのかもしれない。643/1000 苦難は人生のトレーナー そう気づけた瞬間からすべてが変わる
2025/08/21
8月からトレーニングジムに通い始めました。毎回終わるともうクッタクタ。自分一人では絶対に到達できない領域まで負荷をかけられているのが分かります。
その領域に連れていってくれるのは、やっぱりトレーナーの存在。だからこそ身体や姿勢が少しずつ変わっていく。信頼が生まれ、感謝の気持ちが湧いてきます。
一方で、人生にも「苦難」というイベントが必ず訪れます。誰かによってもたらされたり、環境や出来事によって突然降りかかることもあります。これまではそういったストレスに対して、「嫌だけど頑張ろう」「何か意味があるのだろう」と、どこか重い気持ちで、あるいは、誰かや自分を責めながら立ち向かってきたように思います。
でも最近、気づいたのです。これはまだ本質ではなかった、と。あのトレーニングのように、負荷があるからこそ身体が変わるのと同じで、人生の苦難もまた、自分を理想の姿へ導いてくれるトレーナーなのだと。
もちろん、苦難なんてないに越したことはありません。けれど、それが現れるということは紛れもなく変化の兆し。よい方向に向かうしかない、そう思えるのです。
ですから、苦難には喜んで立ち向かう。そんな表現が今の私にはしっくりきます。てなことで、実はトレーナーだったのだと、驚いております。641/1000 一日に100回ありがとう
2025/08/19
今から10年以上前のこと。
日本で一番自動車を売ったという初老の男性とお話する機会があり、その時思い切って質問をしました。
「心掛けてきたことは、なんですか?」
返ってきた答えは、意外なものでした。
「一日に100回『ありがとう』と言うことだよ」
営業の極意といえば、商品知識や巧みな話術を想像していた私にとって、拍子抜けするほどシンプルな言葉。しかし、その後ずっと胸に残り続けています。
売れても「ありがとう」、売れなくても「ありがとう」。お客様に限らず、同僚にも家族にも。日々のささいな場面で感謝を言葉にする。その積み重ねが人の心を動かし、やがて信頼を築くのだと。
私自身、仕事や生活の中で結果や効率を優先してしまい、感謝の言葉を後回しにしていることが多いと気づかされます。だからこそ、あの一言は今も鮮烈です。
もちろん「一日100回」となると簡単ではありません。でも、いきなり大きな数字を目指す必要はない。まずは自分にできるところから。私は最近、ふと思い立って「一日10回ありがとう」を声に出してみようと決めました。
感謝は思っているだけでは伝わらない。口に出すことで、相手にも自分にも温かい余韻を残してくれる。今日もまた、小さな「ありがとう」を積み重ねていきたいと思います。639/1000 夏の夜の余韻と、朝の清掃活動
2025/08/17
昨夜は赤川花火大会が開催され、夏の夜空に大輪の花が咲きました。そして一夜明けた今朝は、打ち上げ場所となった河川敷の清掃活動に参加してきました。私はほんの1時間ほどのお手伝いでしたが、実行委員の方々は今日一日、そしてこれから一週間をかけて片づけをされるそうです。年々評価や期待度が高まる赤川花火大会。その2時間のために、どれほど多くの人の熱が注ぎ込まれているのか、改めて胸に迫ります。
都会からインターンシップで来ていた大学生も清掃に加わっており、花火を観た感想を話してくれました。「これまではスマホで縦に撮るのが普通だったけど、赤川の花火は横で撮らないと収まらなかった」「首が痛くなるくらい高く打ち上がって驚いた」など、素直で新鮮な視点がなんとも面白かったです。
一方の私はというと、ここ数年は家でのんびり息子と音楽鑑賞。昨夜も"かせきさいだぁ"の夏の名曲「じゃ夏なんで」を大音量で流し、大いに盛り上がっていました。
来年はぜひ桟敷席から夜空を仰ぎたい。そんな楽しみを胸に、地域の誇りである赤川花火大会を、舞台裏の片づけからも少しだけ支えていきたいと思います。637/1000 今、習字に向き合う時間が大切なわけ
2025/08/15
習字というのは、手本があって初めて成立します。
けれど手本があるからといって、その通りに書けるかといえば、まったく別の話。筆の速さや力の入れ具合、紙に置く角度──ほんの少しの違いで、全然違う字になってしまいます。
この感覚は、人生や経営にもどこか似ている気がします。
世の中には「手本」と呼べる考え方や成功例があります。けれど、その通りに進めたからといって同じように結果が出るとは限らない。むしろ、そっくり真似してもうまくいかないことの方が多いのかもしれません。
だから大事なのは、手本を「なぞる」ことではなく、自分なりに解釈して消化し、身につけていくこと。習字が一枚ごとに違う表情を見せるように、人生も経営もまた、自分の手で書き進めていくしかないのだと思います。
8級から始めた習字も、気がつけば準初段。いよいよ初段を目指すところまで来ました。まだまだ納得のいく字は書けませんが、その試行錯誤の一枚一枚が、暮らしや仕事の手本探しと重なって見えてきます。635/1000 パッコロ靴で帰る娘と、お盆の墓参り
2025/08/13
空港に降り立った娘は、いつものパッコロ靴に、面積の小さい服、そして長〜い爪という都会仕様のいでたち。
田舎では、こういった人種をまず見かけない。
陽射しを浴びたその姿は、南国ビーチの帰り道か、街角スナップの撮影帰りか——いずれにせよ、この町の景色からは明らかに浮いている。
そんな娘がこれから向かうのは、涼しいカフェでも最新のショップでもなく、お盆の墓地。
しかし、祖父母と父母、そして兄妹と共にお墓前りができることは、大変ありがたく、そして気持ちがいい。
樹木葬などがもてはやされる時代に変わったが、いつもはひっそりしているお寺には、この日ばかりは懐かしい顔がたくさんあった。
母から、戒名の由来や付けられ方の話なども聞けた。
手を合わせられる場所というのは、そこにあるだけで、心の拠り所になる。
時に「お墓は迷惑な物」とされ、樹木葬に移行する話も耳にするけれど、お墓前りは、家族や親族が集うきっかけでもある。
線香の煙の向こうに、笑顔や会話が重なっていく——それもまた、夏の大切な景色だ。633/1000 デスクワークの相棒は、地味なクマ
2025/08/11
今日は事務所に一人、デスクワーク。
最近、姿勢改善のプログラムでトレーナーについてトレーニングをしている。歩き方は教わったが、「じゃあ座っているときは?」と聞くと、意外な答えが返ってきた。
「20センチぐらいのゴムボールを両膝で挟むといいですよ」
さっそく100均へ。
売り場には原色ギラギラのボールや、キャラクター全開の派手なものが並んでいる。迷った末に手に取ったのは、エメラルドグリーンにクマが一匹。派手さはない…と思いたい。何より重要なのは、大きさだ。20センチが条件。ここは見た目より機能優先。
膝に挟んで仕事を始めると、最初は余裕だったが、じわじわ太ももが温まってくる。プルプルするほどではないが、確かに効いている。膝が開かないぶん、背筋が自然にまっすぐになる。
以前、バランスボールに座って仕事をしている会社を見学したことがあった。あれはあれで効果的だが、大きすぎて存在感がすごい。
その点、この“クマのボール”は控えめだ。知らない人が見れば「なんか膝に挟んでる?」程度。オフィスでも自宅でも、静かに姿勢改善できるのがいい。
今日一日やってみて、「これなら続けられそう」と思えた。
最近世間を騒がせているクマさんだが、その視線も、なんだか「姿勢、いい感じだよ」と言っているように見えてくるから不思議だ。631/1000 お盆休みは、静かな事務所で“整理”の原点に戻る
2025/08/09
夜はもう涼しく、エアコンのスイッチを入れなくても過ごせるようになった山形。
明日8月10日から13日まで、当社はお盆休みで、ごみの受け入れはお休みです。
とはいえ、契約のお客様の回収は行うため、出社するスタッフもいます。
私は“グランドスタッフ”として事務所で待機。せっかくの静けさなので、普段は手が届かない場所の掃除や、顧客情報データのアップデートといった「次につながる大仕事」に取り組む予定です。
整理の基本は、不必要なものを取り除き、使いやすくすること。
データのアップデートもまさに整理そのもので、情報を資源として活かす作業です。
実は私は昔からズボラで、整理や片づけは自分とは遠い世界だと思っていました。
ところが前職のQC活動(品質管理活動)で、倉庫整理を任されたことが転機になりました。
QC活動とは、製品やサービスの品質を高めるために職場環境や作業手順を改善していく取り組みで、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)もその一部です。
不要なものを減らし、必要なものをすぐ使えるように配置する。そんな工夫を重ねるうち、棚から棚へと物が魔法のように片付いていく光景に、自分でも驚きました。
「俺、案外才能あるかも」そう感じた瞬間が、自信の種になった気がします。
そしてもう一つ大きな影響をくれたのが、妻の存在です。
結婚前、妻の家に遊びに行くといつも綺麗で、「俺が来るから片付けているんだろう」と思っていました。
しかし結婚してみると、そうではない。朝から晩まで掃除をしているのです。
そんな妻と一緒に取得した整理収納アドバイザーのライセンスが、今の仕事の拠り所になっています。
629/1000 古道具に新たな命を
2025/08/07
今日は、町家ギャラリー&カフェ「古今(ここん)」のオーナー・あい子さんと一緒に、鶴岡で古家具や古道具のリメイク・販売を行っているdenbeeさんの工房におじゃましてきました。
「古今」は、築150年の町家をリノベーションした空間で、地元作家の作品展示や、季節のランチプレートが楽しめる場所。
私たちが家財整理の現場から引き上げてきた古道具たちも、ここで再び光を浴びながら、お客様の目に触れています。
捨てられてしまえば、ただの“ゴミ”として消えていたはずのモノたちが、誰かの手により、空間により、生き直している。
その姿に、私たち自身が励まされている気がします。
そんななか訪れたdenbeeさんの工房。
この道13年というキャリアの中で培った技術を、惜しみなく見せてくださいました。
研磨剤やスポンジの選び方、木肌を活かす磨きのコツ。
「ここは力を抜いて、こっちはじっくり」
一つひとつの動作に、モノへの敬意が宿っているようでした。
でも一番心に残ったのは、その道のり。
「一人でやってると自由はあるけど、立ち上げの頃は…陽が落ちるとどうしようもない不安に襲われてね」
ぽつりと語られた言葉に、静かな重みがありました。
売れない日々に揺れながらも、手を止めず、モノと向き合ってきた時間。
その積み重ねが、今の温かな空間と、人とのつながりにつながっているのだと思います。
私たちの仕事も、ただ“片づける”だけではない。
誰かの記憶を引き継ぎ、次の人の暮らしへと橋渡しするような営み。
その一端を担えることを、あらためて誇りに思えた一日でした。627/1000 講演会、まさかの“無くなりました”
2025/08/05
今日は、ちょっとぼやかせていただきます。
11月下旬に予定されていた、約200人規模の講演会。
私にとっては大きな規模ですし、しかも専門としている整理収納の中でも、新分野にあたるテーマ。
だからこそ、スライドのストーリーを組み立て、そこに合わせて必要なパーツを揃え、足りないピースがあれば現場に足を運び、知識が足りなければ勉強会にも参加して…。
もちろん衣装だって、テーマや参加者層に合わせて準備していました。
そんな中、一本の電話。
「無くなりました」
——以上。
思わず「えっ!」と声が漏れた私に、相手は意外そうな反応。
拍子抜けというより、なんだかモヤモヤだけが残りました。
講演会の依頼って、なぜか対応が雑なケースが多いんですよね。
でも、今回はその中でも残念さが際立つ出来事でした。
…とはいえ、これまでの経験上、準備したものは必ず次に、もっといい形で生きます。
これまでも、そうでしたから。625/1000 高校生に戻る部屋づくり
2025/08/03
今日、実家に避難させていたソファーをついに自室へ持ち込むことにした(息子を助手に)。
これでレコードプレーヤーの前に腰を落ち着け、ジャケットを眺めながら音楽に浸れる。「大人の秘密基地+子供達と音楽で繋がる場」完成である。
…と言いたいところだが、その分だけ掃除はしにくくなる。
妻の視線がレーザービームのように突き刺さる未来が見えるが、そこは「このレコード部屋に、息子もソファーがあるといいねと言っていたという情報」を盾に押し切る予定(子供達を巻き込むと強い)。
それでひとつだけ、あえてやらないことも決めている。
仕事で扱っている古道具は、自室のインテリアには取り込まない。
古道具は素晴らしい。けれど、私の場合、その持ち主や使われ方、その時代背景まで知りすぎている。
そうなると、音楽に没頭するはずの空間で、つい物語の方に引き込まれてしまうのだ。
レコード部屋は、もっと無責任に、ただ「好き」だけで満たしていたい。
そしてもうひとつの決意。
高校生の頃、月に一枚だけCDを買って聴き倒していたあの頃のように、これからは月に一枚ずつLPを揃えていく。
CDがシュルルーと高速で回転する時の高揚感と、ジャケットを手に取ったときのワクワク。
CDはLPに変わるがそんな単純な喜びを、またひとつ増やしていこうと思う。
今日から始まる「高校生に戻る部屋づくり」。
果たして、どんな一枚目から始めることになるだろうか。623/1000 未来の自分がうらやむ“あの頃”
2025/08/01
先日、妻といろんな話をしている中で、こんな話題になりました。
「もしあの頃に戻れるとしたら、いつに戻りたい?」
最近よくある“タイムリープ”もののドラマや映画の影響か、ふたりして妄想が止まりません。
「小学校からやり直すのもいいよなあ」
「就職してから人生の選択を変えてみたいかも」
「いや、あの時、あの人にああ言っていれば…」
やり直したいこと。やってみたかったこと。
過去の“もしも”を並べると、無限にストーリーが浮かんできます。
でも、その話をした翌朝、ふと気づいたんです。
もしかしたら、今この瞬間こそが「あの頃」なんじゃないか?
たとえば、20年後の自分がこの日を振り返ったとしたら、
「ああ、あの頃に戻れたら」と思うかもしれない。
疲れていても、まだ体が動く今。
大切な人と一緒に暮らしている今。
こどもたちが家の中を騒がしく走り回る今。
未来から見れば、きっとまぶしいくらいの「あの頃」。今というあの頃はこれからも無限にあります。
そう思うと、過去に戻ることを妄想するよりも、
今この瞬間を、大切に味わうことの方が、
ずっとリアルで、ずっとすごくいいあの頃だったのだと感じられてきました。
だったら、毎日をもう少し丁寧に、
少し新鮮な気持ちで生きてみてもいいのかもしれないなと。
ということで、暑いですが参りましょうか!
-
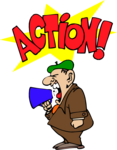 787/1000 必要なのは、答えではない。変化だ
お片づけの現場に立っていると、ときどき首をかしげることがある。なぜ、この家のボトルネックが見えないのだろう。な
787/1000 必要なのは、答えではない。変化だ
お片づけの現場に立っていると、ときどき首をかしげることがある。なぜ、この家のボトルネックが見えないのだろう。な
-
 789/1000 面接官を仰せつかった夜
末の娘の高校受験が近づいている。学校でも面接練習が始まっていて、どうやら娘は「模範的な回答」を一生懸命、覚えて
789/1000 面接官を仰せつかった夜
末の娘の高校受験が近づいている。学校でも面接練習が始まっていて、どうやら娘は「模範的な回答」を一生懸命、覚えて
-
 891/1000 見えない壁をぶち壊す
当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの
891/1000 見えない壁をぶち壊す
当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの
-
 793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
-
 795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ