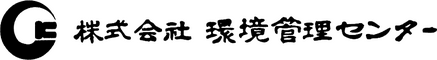| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
843/1000 整うとは、認知することかもしれない
2026/03/13
人は歳を重ねると丸くなる、と言う。
自分はどうだろうかと考えてみる。
プライドがなくなったかというと、きっとそんなことはない。
量は昔と同じなのだと思う。
ただ、扱い方が少し変わった気はしている。
昔は小さな鍋で煮ていたから、
すぐに煮立ってしまった。
今は少し大きな鍋になったのかもしれない。
それともローリエを一枚入れて、臭みを取る調理法を覚えたのか。
どちらにしても、
少し扱いやすくなった気はしている。
対人関係の中で、
自分の小さなプライドに気づくことがある。
特に、自分がどこかで下に見ていた人から
指摘されたときだ。
その瞬間、心の中で反発が生まれる。
「そんなこと言われる筋合いはない」
そんな気持ちが一瞬よぎる。
でも同時に、
「ああ、今いいカッコしようとしたな」
「いらないプライドだな」
そう気づく自分もいる。
プライドそのものは、きっとなくならない。
ただ、それを認知できるかどうか。
それが大事なのだと思う。
気づけば、少し修正できる。
気づかなければ、そのまま反応してしまう。
整理の仕事をしていると、
整えるとは、物を減らすことだと思われがちだ。
しかし本当は違う。
まずは
そこにあることに気づくこと。
そこから整えることが始まる。
人の心も、
案外同じなのかもしれない。
841/1000 AIが作るブルーワーカーの時代
2026/03/11
ブルーワーカーの時代が来るとは思っていなかった。
若い頃、世の中にははっきりとした空気があった。
頭を使う仕事が上で、体を使う仕事は下。そんな見えない序列のようなものだ。
特にゴミの仕事は、その中でも下に見られていた感が強かった。
今なら言葉を選ぶ人も多いだろうが、当時は普通に差別のようなものもあった。
子供の頃は、それを強く感じていた。
恥ずかしいというよりは、
相手がどうしても偏見を持ちたがる。
そんな空気を子供ながらに感じ取っていた。
そして後になって知ったのだが、
この仕事をしていることで、子供が学校で嫌な思いをする。
それが理由で仕事を辞めたスタッフもいたと聞く。
それほど、この仕事は世の中から低く見られていた。
これまで映画やドラマでも、
この仕事は「行くところがない人がやる仕事」のように描かれることが少なくなかった。
それに関しては、正直なところ我慢ならない。
社会は必ずゴミを出す。
そしてそれを回収し、分別し、資源として循環させる人がいなければ、
社会は一日たりとも回らない。
つまりこの仕事は、社会の裏方ではあるけれど、
社会を支える基盤の仕事でもある。
最近はAIの話題をよく耳にする。
文章を書き、資料を作り、データを分析する。
これまでエリートと呼ばれてきた仕事の中には、AIに置き換わっていくものも増えていくだろう。
では、現場の仕事はどうだろう。
重たいものを持つ。
現場の状況を見て判断する。
人と話しながら段取りを組む。
こういう仕事は、簡単にはAIに代われない。
ブルーワーカーの時代。
そんな時代が来るとは思っていなかった。
だから私は、この仕事をもっと磨いていきたいと思う。
胸は張る。
だが、威張るのとは違う。
社会の循環を支える仕事を、
静かに、誇りを持って続けていく。839/1000 英検面接と、襟付きニット
2026/03/09
昨日は息子の英検の面接試験の送迎をしていた。
英語の試験といっても、筆記ではなく面接だ。英語力だけではなく、コミュニケーションとして成立するかどうかを見られる試験らしい。
前回は不合格だった。理由は「態度」。
英語の内容ではなく、評価項目の態度で減点されたということで、息子的には少し納得がいかなかったようだ。
そこで今回は対策を考えたという。
相手の目を見て話す。
手を机の上に出して組む。
そして、自信がある自分を精一杯演じる。
なるほど、と思った。高校生なりに面接というものを観察し、どう振る舞えばよいかを考えたのだろう。
服装は自由ということで彼は、ライトグレーの太めのスラックスに黒のVネックで出かけようとした。それでも悪くはないが、私は少し気になった。
「襟付きの方がいいんじゃないか」
面接というのは内容だけではなく、その人がどう見えるかという総合力が問われる。襟があるかないかだけでも、マナーを知っている人なのかという印象が変わるものだ。
このぐらいの男子に服装のことを言うと、たいてい反抗される。しかし息子は特に文句も言わず、ボタン付きの襟付きニットに着替えてきた。
試験が終わり、迎えに行くと、車に乗り込んできた息子は少しだけ表情が明るい。
「どうだった?」
「うん、今回は手応えあった」
結果はまだ分からない。
社会に出ると、人はさまざまな場面で役を演じる。
営業なら営業の顔、講師なら講師の顔。最初は演技のようでも、やがてそれが自分の型になる。
自信というのは、最初からあるものではない。
こうして少し背伸びをして、自信のある自分を演じるところから始まるのかもしれない。
837/1000 暮らしの動線を整える
2026/03/07
今週も土曜日は会社はお休み。
令和8年の3月は基本的に土曜日が休みですが、21日だけは営業日となっています。
とはいえ、完全に休んでいるわけではありません。
お見積もりなどは、できる限り対応しています。
そんな訳で、本日も一件、お見積もりに行ってきました。
最近ご相談が多いのが、90代の男性のお宅の整理です。
今回の目的はとてもはっきりしていました。
転倒の防止。つまり動線の確保です。
高齢になると、ちょっとした段差や物の多さが事故につながります。
だからまず行うのは、物量のコントロール。
つまり、必要以上に増えた物を減らすことです。
ただ、ここで終わらないのが整理の仕事です。
物が減ると、本当に必要な物が見えてきます。
それらを
・使用するシーン
・使用頻度
・使う場所
といった視点で分類していきます。
毎日使うもの。
外出のときに使うもの。
来客のときに使うもの。
季節で使うもの。
そんなふうに、暮らしの場面と頻度の両方から整理していく。
そして分類ごとに収納を整えていきます。
本日のご相談は、収納の提案までという内容でした。
単に物を捨てるというご依頼よりも時間はかかります。
けれど、こうして整えた環境は
リバウンドしにくく、使いやすく、何より安全です。
整理とは、物を減らすことだけではありません。
暮らしの動線を整える仕事。
そんなことを改めて感じた一日でした。835/1000 200年という物差し
2026/03/05
ビジネスというものを、もし200年という時間で考えたらどうなるだろう。
そう思うと、少し面白くなる。
今、私たちが必死に取り組んでいる仕事のほとんどは、きっと200年後には存在していない。会社も、商品も、仕組みも、社会の形すらも、きっと大きく変わっているはずだ。
200年前の人たちが必死にやっていた仕事を、今の私たちはほとんど知らない。それと同じことが、これから先にも起きるのだろう。
そう考えると、なんだか肩の力が抜ける気もする。
しかし不思議なことに、日々の仕事はそう簡単にはいかない。
目の前には、今日決めなければならないことがある。
人のこと、会社のこと、未来のこと。
一つひとつ、とことん悩む。
たぶん、その繰り返しが仕事なのだろう。
200年後には残らないかもしれない。
それでも、今日という一日は確かにある。
その一日の中で、悩み、考え、決める。
その積み重ねが、会社という形になり、仕事という形になり、誰かの暮らしにつながっていく。
200年という時間の中では、ほんの一瞬の出来事なのかもしれない。
それでも、その一瞬を真剣に生きる。
ビジネスというのは、案外そんな営みなのかもしれない。
-
 829/1000 東京は毎日がお祭り
コスプレの集団が行き交い、サンタクロースのような風貌の外国のおじさんが、小脇にブラックニッカを抱えて酩酊してい
829/1000 東京は毎日がお祭り
コスプレの集団が行き交い、サンタクロースのような風貌の外国のおじさんが、小脇にブラックニッカを抱えて酩酊してい
-
 831/1000 希望と覚悟の三月
今日から三月。息子を高校の卒業式へ送っていった。彼は在校生として参加、校門には晴れ着姿の父母が並び、春の光が少
831/1000 希望と覚悟の三月
今日から三月。息子を高校の卒業式へ送っていった。彼は在校生として参加、校門には晴れ着姿の父母が並び、春の光が少
-
 833/1000 必殺技は一つでいい
昔、ゼミの先生から教わった言葉がある。「必殺技は一つでいい。」名だたる格闘家といえど、決め技は一つ。その技が最
833/1000 必殺技は一つでいい
昔、ゼミの先生から教わった言葉がある。「必殺技は一つでいい。」名だたる格闘家といえど、決め技は一つ。その技が最
-
 835/1000 200年という物差し
ビジネスというものを、もし200年という時間で考えたらどうなるだろう。そう思うと、少し面白くなる。 今、私たち
835/1000 200年という物差し
ビジネスというものを、もし200年という時間で考えたらどうなるだろう。そう思うと、少し面白くなる。 今、私たち
-
 837/1000 暮らしの動線を整える
今週も土曜日は会社はお休み。令和8年の3月は基本的に土曜日が休みですが、21日だけは営業日となっています。とは
837/1000 暮らしの動線を整える
今週も土曜日は会社はお休み。令和8年の3月は基本的に土曜日が休みですが、21日だけは営業日となっています。とは