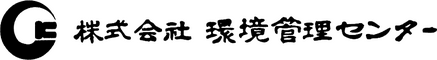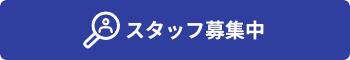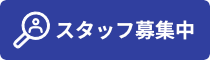| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
649/1000 花札から能の舞台まで──芒に月と食卓の会話
2025/08/27
昨夜の食卓で、末の娘が兄に尋ねた。
「ねえ、この曲のタイトル、なんて読むの?」
スマホから流れていたのは、椎名林檎さんの新曲『芒に月』。今年の6月に出たばかりの曲だが、“芒”の字は娘にはなじみがなかったらしい。
どこで知ったか知らないが、兄は少し得意げに答えた。
「“すすきにつき”って読むんだよ。花札の札がモチーフになってる。」
そこから食卓は、ちょっとした花札講座に。
「シカトって言葉も花札用語で、鹿の札を取られない=無視するって意味からきてるんだ。」
「へえ〜そうなんだ!」
家族みんなで感心しながら、私も横で初めて知ってうなずいた。さらに今日知ったトリビアとして、物事を終えるときに使う「仕舞う」も実は能の舞台から来ているという。舞の最後を納める所作を「仕舞い」と呼び、そこから物事を美しく終えることを「仕舞う」と言うようになったのだとか。
私たちお片付けの現場でも、この「仕舞う」をどうプロデュースするかがいつもカギになる。647/1000 ドームも神宮も横浜も、父まだ未経験
2025/08/25
お盆で帰省した娘が、最近ハマっているのは野球観戦だという。
巨人ファンで、なんと月に3回も東京ドームや神宮球場、横浜スタジアムに足を運んでいるらしい。
「イケメンが多いのはソフトバンクなんだよ。細マッチョが多くてさ」
スマホの画面を見せながら熱弁する娘。その写真の中に父親が入り込む余地は、もちろんない。
思い出すのは、彼女が高校1年の頃。母校が甲子園に出場した時、「せっかくだから応援に行ってこい」と言ったら、娘は一言、
「また行けばいいから」
あの時のあっけらかんとした返事が今も耳に残っている。
結局、あの夏は一度きりだったのに。
そんな娘が今や、プロ野球観戦に夢中だとは。
アラフィフの父はというと、ドームも神宮も横浜も、まだ一度も行ったことがない。
そのうち娘に連れて行ってもらおうか──そんなことをぼんやり考えている。
横で野球を全く知らない高校生の息子に、娘が熱弁をふるう。
「江夏豊っている?」と息子。
そんな会話を聴きながら、父はただビールを一口。
家族のこういう時間が、なんだかんだ一番面白い。645/1000 さあハロウィンがやってくる。 知らんけど
2025/08/23
三日前のこと。通勤の道すがら、ぽとりと栗が落ちていた。見上げると、葉の間にまだ丸々とした実がいくつもぶら下がっている。ああ、秋だなと思う。買い物に立ち寄った店では、ハロウィンの飾りがずらりと並び、かぼちゃのお化けが笑っている。子どもの頃にはなかった光景だ。
ハロウィンが日本にやって来たのは、私が二十代前半のころだっただろうか。だけど正直、いまだにその正体はよく分かっていない。
さて、もうひとつ、最近思い出したのが三遊亭円右師匠の「クリスマス」という落語である。戦後しばらくの日本人が、クリスマスという異国の行事を“よく分からないまま”受け入れていた頃の空気が漂っている。昔の落語家さんは、イブを大晦日、クリスマスを元旦のようなものだと説明していたそうだ。つまり年越しと同じように浮かれ、同じように迎えればいい。だけど庶民にとっては、やっぱり「なんのこっちゃ」である。
円右師匠の「クリスマス」は、ちょっと世知辛くて、でも人間くさい。聴いた人が「こんなクリスマスだけは嫌だ」と思ったというのも分かる気がする。そう考えると、ハロウィンやクリスマスは、分からないまま笑いながら受け入れてきた文化の象徴なのかもしれない。643/1000 苦難は人生のトレーナー そう気づけた瞬間からすべてが変わる
2025/08/21
8月からトレーニングジムに通い始めました。毎回終わるともうクッタクタ。自分一人では絶対に到達できない領域まで負荷をかけられているのが分かります。
その領域に連れていってくれるのは、やっぱりトレーナーの存在。だからこそ身体や姿勢が少しずつ変わっていく。信頼が生まれ、感謝の気持ちが湧いてきます。
一方で、人生にも「苦難」というイベントが必ず訪れます。誰かによってもたらされたり、環境や出来事によって突然降りかかることもあります。これまではそういったストレスに対して、「嫌だけど頑張ろう」「何か意味があるのだろう」と、どこか重い気持ちで、あるいは、誰かや自分を責めながら立ち向かってきたように思います。
でも最近、気づいたのです。これはまだ本質ではなかった、と。あのトレーニングのように、負荷があるからこそ身体が変わるのと同じで、人生の苦難もまた、自分を理想の姿へ導いてくれるトレーナーなのだと。
もちろん、苦難なんてないに越したことはありません。けれど、それが現れるということは紛れもなく変化の兆し。よい方向に向かうしかない、そう思えるのです。
ですから、苦難には喜んで立ち向かう。そんな表現が今の私にはしっくりきます。てなことで、実はトレーナーだったのだと、驚いております。641/1000 一日に100回ありがとう
2025/08/19
今から10年以上前のこと。
日本で一番自動車を売ったという初老の男性とお話する機会があり、その時思い切って質問をしました。
「心掛けてきたことは、なんですか?」
返ってきた答えは、意外なものでした。
「一日に100回『ありがとう』と言うことだよ」
営業の極意といえば、商品知識や巧みな話術を想像していた私にとって、拍子抜けするほどシンプルな言葉。しかし、その後ずっと胸に残り続けています。
売れても「ありがとう」、売れなくても「ありがとう」。お客様に限らず、同僚にも家族にも。日々のささいな場面で感謝を言葉にする。その積み重ねが人の心を動かし、やがて信頼を築くのだと。
私自身、仕事や生活の中で結果や効率を優先してしまい、感謝の言葉を後回しにしていることが多いと気づかされます。だからこそ、あの一言は今も鮮烈です。
もちろん「一日100回」となると簡単ではありません。でも、いきなり大きな数字を目指す必要はない。まずは自分にできるところから。私は最近、ふと思い立って「一日10回ありがとう」を声に出してみようと決めました。
感謝は思っているだけでは伝わらない。口に出すことで、相手にも自分にも温かい余韻を残してくれる。今日もまた、小さな「ありがとう」を積み重ねていきたいと思います。-
 795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
-
 797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
-
 797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
-
 799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
明日から二泊三日の東京出張に備えて、段取り中。 大雪の庄内から晴天であろう東京へ行くので、まず靴から考える。
799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
明日から二泊三日の東京出張に備えて、段取り中。 大雪の庄内から晴天であろう東京へ行くので、まず靴から考える。
-
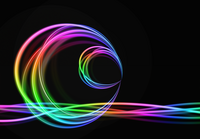 801/1000 経営というメンコ合戦
東京出張二日目。中期経営計画を立てる勉強会に参加している。利益、戦略、数字、未来。ノートを取りながら、改めて目
801/1000 経営というメンコ合戦
東京出張二日目。中期経営計画を立てる勉強会に参加している。利益、戦略、数字、未来。ノートを取りながら、改めて目